再生のヒントは
自然のなかにある
千代田:松島さんとはかつて同じトレイルランニングチームに所属していたんですよね。それからのお付き合いだから、かれこれ7〜8年くらいになりますか。
松島さんにご登壇いただいた沼津でのイベントを終えた後、自分の中で「Webメディアをつくりたい」という想いがどんどん募っていって、今回『Regenerate Magazine(リジェネレートマガジン)』というメディアを立ち上げることにしました。僕らはメディアをつくること自体初めてなので、『WIRED』で多彩な切り口から誌面をつくっていらっしゃる松島さんに、今日はいろいろ伺いたいなと思っています。

松島:メディアを立ち上げるというのは面白いですね。イベントに参加したとき、「リジェネレート」という広い文脈を持つ言葉からひとつのイベントをまとめ上げてしまう千代さんの実践力に驚いたんです。強い想いが伝わってきたし、すごく編集的視点が入っているなと感じて。
自分たちが楽しんでいるアウトドアを、リジェネレートという方向性で編み上げるとこういう形になるんだなと思いましたね。「再生」を概念的に捉るのではなくて、「リジェネレートは自分たちの好きなアクティビティと地続きなんだ」ということが深く理解できる体験になっていましたよね。出展ブランドも普段から環境活動を行っている人たちもいれば、そうじゃない人たちもいて、そのミックスが面白かった。
千代田:来場してくださったお客さんからも「普通のイベントじゃなくて、各ブランドがそれぞれの方法で再生のアンサーを伝えながら商品説明してくれた」という声をいただいて、すごく嬉しかったですね。
松島:リジェネレートって、すごく懐の深い言葉でしょう。『WIRED』でも今年「Future Regenerative」というテーマでカンファレンスを開催したんだけれど、そこでは未来の再生について「City」「Commons」「Selfcare」という3つのテーマを掲げたんです。
ただ単に再生という言葉を取り出すだけだと、「再生プラスティックボトル」みたいなイメージになってしまうけれど、リジェネレートには「何度でも生まれてくる」というニュアンスがある。そこが深いというか、それをどういう形で僕らが受け止められるかが鍵だなと思っているんです。目の前のものをもう一度再生して使うということ以上の視点があるはずだなと思っていて。
千代田:『WIRED』は俯瞰した視点から未来を語るメディアで、未来に対して希望が持てるような技術や開発が切り口になっているところにすごくワクワクさせられます。そうしたメディアをつくる中で、松島さんが常に身体に重きを置いているのが自分と共通する部分だなと思っているんです。
これからリジェネレートマガジンをつくっていくにあたって、たとえば自分なりの挑戦をしている人たちのマインドなんかも、僕はすごくシンクロしてくると考えているんですね。なぜそういうチャレンジをしたのかという視点は、僕らが圧倒的に惹きつけられる要素です。

松島:パーソナルストーリーはやはり強いよね。
千代田:ですよね。松島さんは2018年から『WIRED』日本版の編集長をされているわけですけれど、昔から一貫して興味を抱いているものって何かありますか。
松島:『WIRED』は元々1993年に米国・サンフランシスコで創刊されたメディアで、僕も学生時代からかれこれ四半世紀読んでいるので、自分の興味とすごく重なる部分が大きいんですね。
ひと言で定義するときには「テックカルチャー・メディア」という言い方をよくするんですが、テクノロジーを考えるとき、僕はよく足のことを考えるんです。僕は素足にルナサンダルを履いて走るんだけれど、皮膚というのは最先端のテクノロジーよりも偉大なんですよ。なぜかというと、ちょっとくらい破けても皮膚は治ってくれるから。靴ならアッパーが破けたりソールがすり減ったりしたら新しい靴に替えますけれど、裸足は再生する。この最先端ツールに人間のテクノロジーはまだ追いついていないわけです。そういう意味では、再生の原型って自然の中にあるんですよね。だから自然の中に身を置くことは、僕らが未来のヒントを見つける行為なんだと思います。

千代田:確かに、それはありますね。自然に触れる体験はいちばん再生について理解しやすいと思います。自然の中に身を置くことで地球の大きさも感覚として把握することができるし、そういうことをしないとなかなか環境のことを自分ごととして捉えられないんじゃないかと思います。リジェネレートについて考えるようになってから、僕も山に行くとそういうことを感じるようになりました。
松島:まさにそう、自然に対する畏怖といったものが人間には必要だと思う。その一方で、石器時代から人間は自然を改変しながら文明をつくってきたわけで、いまや無垢なる自然なんて幻想だと言われている。だから自然をどう捉えるかについてはバランスがとても大事だと思いますね。
メディアの役割は
文脈の選択肢を見せていくこと
松島:そうしたバランスのなかで、一人ひとりが生きていく上で大事にしたい価値観や生き方を見極めることが重要だなと思います。その手助けをするのがメディアであって、メディアの役割の大切なひとつは「深い洞察を与えること」だと思うんですよ。
『WIRED』は創刊時に、これから起こるデジタル革命を人類が火を扱えるようになったときに匹敵するほどの文明の変化だと定義しました。そして、単に先端テクノロジーを伝えるのではなく、そこに意味と文脈を与えていくことこそが究極のラグジュアリーだと宣言して、長年マントラのように唱えてきました。
つまり、情報やニュースはいくらでもあるけれど、それはどういう意味でどういう文脈で読むべきなのかというアングルを提示してあげることが『WIRED』の仕事ではないかと考えています。だから時には「ニュースなど見なくていい」と極端な表現をしたりもします。

文脈は重要ですよね。地球環境が危機的状況だとかプラスチック問題が深刻だというファクトはいまや誰でも知っているんだけれど、それが自分の生活のなかに文脈として入ってこないと、いつまでたっても人ごとに思えてしまう。でも千代さんが提唱しているような「自然の中のアクティビティを通して入っていくこと」というのは自分ごとにできます。それは翻ってみれば、都市生活の中でもできることなのかもしれないなと。
庭先で養鶏を始めたのもそういう想いがあったからなんです。実際に試してみると、循環とはこういうことなんだなというのが等身大でわかるんです。そうはいっても鶏のことを考えるのなんて一日のうち3分くらいなんだけれど、たった3分でも毎日鶏との触れ合いがあると、そこが取っ掛かりとなってもっと大きな問題、例えば循環型経済といったことを身をもって考えられる。そのための文脈の選択肢を世の中に提供してあげるというのが、メディアにとって重要なことかなと思います。
千代田:なるほど。養鶏もそういう視点で始めたんですね。
松島:『WIRED』雑誌版の「New Commons」がテーマの号で、創刊編集長のケヴィン・ケリーがこんなことを言っているんです。「未来に対するソリューションを手渡すのではなくて、選択肢と選択できるツールを用意することが自分たちの役割だ」と。
解決策を提示することも大切なんだけれど、おそらくその解決策自体が未来においては新たな問題になっているはずだというわけです。だからいまあるツールや技術、ソリューションに対して僕らは謙虚でなければいけない。いま目の前にあるものがベストだと思って生きているけれど、それが永遠にベストなわけではないということです。
『WIRED』は未来を扱うメディアなので、あとから過去を振り返っていくらでも採点できるんですよ。当たり外れはもちろんあって、テクノロジーだけでなく環境に関しても、当時はいいと思っていたことが後になると良くないということはあるんじゃないかと。
千代田:そういうことは往々にしてありますよね。
松島:だから僕らは謙虚でなくてはいけないんだけれど、一方で、倒れるなら前向きに倒れたい(笑)。人間は必ず失敗するのだから、そのときに自分たちが大切だと思うものや面白いと思ったものをちゃんと出していこうというのが『WIRED』のスタンスです。僕らは報道機関じゃないので、こうした自分たちの態度をどうやって表現するかが使命だと思っています。
千代田:『WIRED』がそういうスタンスだというのは、とても勇気づけられます。僕らはまだ歩き始めたばかりで、松島さんの話にあった「マントラ」のように反芻するもの自体をつくってはテストしている段階。未来にはそれも調整が必要になってくるかなとも思います。
でもリジェネレートという考え方は、ここから10年20年先まで興味あるものごとになっていきそうだなと感じているんです。僕らノマディクスと一緒にたくさんの人たちが手を繋げるキーワードなんじゃないかと思っています。

方法論より
内面の変化に興味がある
千代田:鶏を飼って何か気づきがありましたか?
松島:僕は10年ほど前にデジタルファブリケーションやメイカームーヴメントの代表作である『MAKERS』という翻訳書を手掛けたときに、マーク・フラウエンフェルダー著『MADE BY HAND』という本を読んで以来、ずっと養鶏がやりたかったんですね。著者はかつて『WIRED』の編集部にもいたことがあって、雑誌『MAKE』の編集長もしていたんですが、まさに日々の生活のなかのメイカームーヴメントを紹介した本で、その中の一章では、西海岸に住んでいる彼が庭で鶏舎づくりをするんです。電気で自動開閉する鶏舎の扉をDIYしたりしてすごく凝るんだけれど、結局コヨーテに鶏舎を襲われて最後は諦めてしまうというほろ苦い終わり方で。
でもそれを読んだときに、最先端のデジタルツールを使って養鶏を始めるなんてなんてカッコいいんだ、と感じたんです。それでいつかやりたいと思っていた鶏舎づくりを2021年のGWにやろうと決意し、もう一度その本を読み直しました。
千代田:たとえば「田舎暮らし」と一言でいっても、一般的な人たちが想像するスタイルって1000通りくらいあるじゃないですか。畑をやるにしても肥料はあげるのかあげないのかとか。田舎暮らしにしても養鶏にしても、いわゆるステレオタイプなイメージだけじゃないですよね。僕は自宅にコンポストを取り入れたときにそう感じました。取り入れ方には個々のスタンスがあるわけで、そうした生活全般から映し出される考え方が、これからはすごく重要になってくるんじゃないかなと。
僕らがやろうとしていることはテックメディアではないので、方法論よりも、それを取り入れたことによる内面的な変化が興味の対象になってくると思います。だから松島さんが養鶏を始めたことで、どんな内面的な変化があったのかに自分は興味があります。

松島:その感覚わかります。たぶん養鶏を始めたのは、鎌倉に越してきたことと相似形だと思う。東日本大震災が発生したとき、僕は高輪のタワーマンションに住んでいて持続不可能性を目の当たりにしました。そういう経験をした後、ささやかだけれども少しでも自立した生活というか、現代のシステムから自立した生活をどうやったら確立していけるかを探り出そうと思ったんです。養鶏も端的にいえば卵を自給自足するということなんですよね。
もうひとつ、これは東京大学の熊谷晋一郎先生がおっしゃっていることなんだけれど「自立するということは人に頼らないということではなくて、頼る先をたくさん持つことだ」という考え方があります。鎌倉に引っ越してきたのはまさにそれで、都心のマンションだと隣近所誰にも頼れないけれど、鎌倉では近隣の人たちとの付き合いがあって、頼れる人がたくさん生まれました。

千代田:持続不可能性を実感しての選択だったわけですね。
松島:そう。それで庭先養鶏については、三浦半島にある「sho-farm」という農園を参考にしています。養鶏で得られる物理的なものはしょせん卵なので、システムにお金をかけてはいけないという考え方に立っています。だから餌は米ぬかやくず米、残飯だし、養鶏場も廃材を使っているし。鶏は米ぬかが大好物なんだけれど、我が家はお米をほとんど食べないので、自宅で精米している友だちから米ぬかを分けてもらったり、地元でこれまで存在すら気に留めなかったお米屋さんに行って、100円で米ぬかをたくさん売ってもらったり。あとは材木屋さんで鶏舎に敷く木くずを分けてもらったり。
養鶏を始めたことで生まれたネイバーフッドでの出会いがあって、依存することで自律するような関係性を、ローカルのなかでいままで以上に構築し始めることができました。
自然とどう対峙するかが
テクノロジーを進化させた
松島:30年後の生活を思い浮かべるとき、SF的な生活を思い浮かべる人もいれば、一方では30年後もいまと変わらないんじゃないかと思っている人たちもいるんですね。ただわかっているのは、僕らがいま電気を意識せずに使っているように、30年後はAIを誰もが意識せずに使うようになるということ。冷蔵庫が電気で動いていることを誰もいま意識しないように、AIやロボットが普通に生活に結合しているでしょう。
100年前の人から見たら、いま僕らが電気を意識せずに使っている生活というのは想像できないんだけれど、それでも人間の営みの根本は何十万年も変わっていなくて、そこにテクノロジーがミックスされてきただけということだと思います。
でもそのテクノロジーはアンバランスであって、時代ごとに変化していく。この100年200年は、自分たちがつくった都市の中でどう快適に過ごすかがテーマで、自然とどう対峙するかという観点からテクノロジーが発達してきました。これから人間は何を拡張していくのか。身体性なのか感性なのか、それとも人間の外にあるAIなどを拡張していくのか。いずれにせよそれ自体は目的ではなくて、何かをするための手段に過ぎないんです。そうした手段としてのテクノロジーとどういう付き合い方をしていきたいかと考えた先に、それが未来として実装されていくのかなと思います。
でもテクノロジーが一番進化する場所がどこかといえば、たとえば大航海時代の探検だとか極地への冒険みたいなところなんですよね。そういうところでも生きられるようにテクノロジーの進化が起こってきた。冒険に必要なものをつくって、それらが技術転用されて、僕らが普段の生活で使うようになってきたというのがこれまでのテクノロジーの普及の仕方だと思うんです。
そういう意味では、リジェネレートみたいな自然の中のアクティビティを好む人たちが見ていく世界というのが、先行事例になるんじゃないのかな。そういう人たちがどういうテクノロジーを選んで、何を捨てていくのかということがね。
千代田:進化したテクノロジーが存在するから、捨てることができるんですよね。

松島:鎌倉に引っ越してきたときには、これほどまで自宅で働くようになるとは思っていなかったけれど、ZOOMなどのリモートワークを推進できる機能が充実してきたことでそれが可能になっているんですよね。でもそこには膨大な電気が使われていて、技術の進化があるからこそ人間は自然に還れる部分もある。そう考えると、二つの側面の両立があるのだと思います。
歴史や伝統から学ぶことで
未来が見えてくる
千代田:第一回目のイベントが終わった後、僕は一ヶ月くらい虚脱してしまって、自分の中で咀嚼するのに時間がかかったんですね。それはなぜかというと、そもそも再生って必要なことなのかなと考えてしまったから。再生のイベントをやって、再生が必要なのかを考えるなんて太宰治かよという感じなんですけど(笑)。
テックなど『WIRED』で取り上げるものは最先端技術の未来だけれど、僕らが普段、生活の中で接する文化や伝統工芸などは長い年月を経ているものじゃないですか。それが暮らしに浸透していたり、生きて行く手段になっていたり。

自分たちはいまものごとの境目にいると思うんですよね。先ほど何を未来に選択していくかという話がありましたけれど、たとえば「自分はテスラを買って行動していこう」という選択と、「歴史の中で培われてきた道具を使おう」という選択の両方を取り入れることができる時代に生きているんだなと感じるんです。すごく自由度があるなと。
僕らは、その両方の世界を行ったり来たりしながら再生していくんだなと思うんですよ。再生というのは人間の細胞レベルでいえば止められないものなわけで、毎日僕らは再生していくし傷も治っていく。再生をただ繰り返して生きているんです。意図せずとも繰り返していくものが再生であるのならば、ただぼーっと過ごして無関心でいるよりも、自分なりに考えて気持ちよく選択していきたい。
伝統や歴史の中で培われてきた生活様式など民俗学的なものと、未来のテクノロジーは両輪で、僕らはこれから何を進めて何を戻っていくのか。2021年に鶏を庭で飼うことが真新しく感じるというのは、すごく開かれた時代なのかなという気がしています。
前向きに捉えれば、いま変わるきっかけに溢れていると思うんですよ。もちろん変わりたくない人もいると思うんだけれど、この流れを一つのケースとして、リジェネレートという切り口で照らしていくことが、僕がやっていきたいことなんだというのが、一ヶ月の咀嚼期間を得て出てきた答えです。過去もすごいと理解していないと、未来の選択もできないよなと思うんです。

松島:歴史から学ぶことは重要で、その積み上げの先にしか未来はないんだよね。火はまさに衣食住すべてに関わる人類の歴史で、火が人類の何を変えてきたのかを学ぶだけでも何十万年の歴史を学べることになる。そこから考えられることって多いと思うんですよ。
火を使って料理をすることで体にカロリーをたくさん取り入れることができるようになり、脳が膨らんでホモサピエンスが誕生した。いま僕らは外付けのハードディスクやクラウドで同じことをしているんです。自分の脳で電話番号を覚えなくてもよくなって、自由に脳が拡張できるようになった。生物学的な意味でいう脳は大きさも含めてほとんど変わっていないんだけれど、いま急激に拡張し出しているわけです。
脳が拡張したことで文化が始まりました。たとえば想像上のものごとを絵に残したり、人に伝えたりすることは文化の始まりであって、ある種の認知革命ですよね。そう考えると、脳が拡張することによって、これから新しい認知革命が起こって新しい文化をつくっていくことになる。人類がこれまで歩んできたことを振り返ると、未来も想像できるわけです。

伝統文化についても同様で、伝統文化は各時代の新しいテクノロジーを取り入れながらリジェネレートとしてきたわけですよね。そうした伝統文化を2021年の感性で受け止めることで、そこに新しいインタラクションが生まれてくるんじゃないかな。
千代田:そういう切り口でいうと、このリノベーションされた素敵なシェアオフィスも、古い家屋を違う観点から体験するという意味で興味深いですね。
コロナの影響は
身体にどう及んだか
松島:コロナの影響によって、屋外で思うように身体が動かせない状態が続いていましたよね。鬱や自殺の増加も、身体を動かせないことが少なからず影響している気がします。
僕が10年前に編集した翻訳書『脳を鍛えるには運動しかない』(ジョンJ.レイティ&エリック・ヘイガーマン著/NHK出版)がいますごく売れているらしくて、大増刷したんです。身体と気持ちのコネクションに対する興味は世の中ですごく高まっているんじゃないかなと思います。リモートによって身体性を伴わないコミュニケーションが増えていく中で、心の状態をつくるのは身体的なものだということに意識が向いているのかなと感じますね。

千代田:心と身体は密接に繋がっていますよね。社会的には価値観の多様性が広がっていて、「こうなりたい」と思えるようなインフルエンサーがものすごくたくさん存在している。広告やWEBの世界に浸って情報過多になっていると、もう昭和のようなステレオタイプの幸福の形にはみんな満足しなくなっているわけです。誰もが憧れる絶対的ヒーローはもはや見つけにくいんですよね。だから誰かの個人的なチャレンジとか身体的な極限を目指す世界なんかに、みんながすごく気持ちを乗せて応援したくなるんじゃないかなと。
ただそこから何かを感じた後に、「裏山にちょっと行ってみようか」とか「川に下りてみようか」といったアクションを起こせる人と、そのままベッドルームで寝ている人がいる。ベッドにいてもスワイプすることで疑似体験ができてしまうから、それだけでも満たされるんだけれど、筋肉を動かして体温の高まりや疲労を感じたりすることはすごく大事なんじゃないかと思います。つまり、次のアクションが起こせるかどうかが重要なんじゃないかなって思うんですよ。自分なりのウェルビーイングのカードをどれだけ持っているかが人生の豊かさに繋がるのかなと。

松島:いまの話、すごく共感したな。僕が鎌倉に越してきたときに打ち出したかったのは「トレイルランは日常であってレースではない」ということなんです。トレイルを走ることは非日常でなくて日常であるということ。
こういうことを話すとたくさんの人を敵に回すかもしれないんだけれど、コロナ禍でトレイルランのレースが次々と中止になったとき、もちろん準備や経済面ではみんな大変だったはずだけれど、「走る」というメンタルの面では僕は1ミリも困らなかったんですよ。天気とか関係なく決まった日に走らなければいけないレースという形が、もともと僕はあまり好きじゃないんです。もちろん、レースという形態としてそれは仕方がないことなんだけれど。
今回のコロナにしても、そういうことを考えるきっかけになればいいなとは思います。目標のレースがなくても山に入って走っていたら楽しいし、それを感じることができたら、自分なりのウェルビーイングのカードを一枚持てることになるわけですよね。
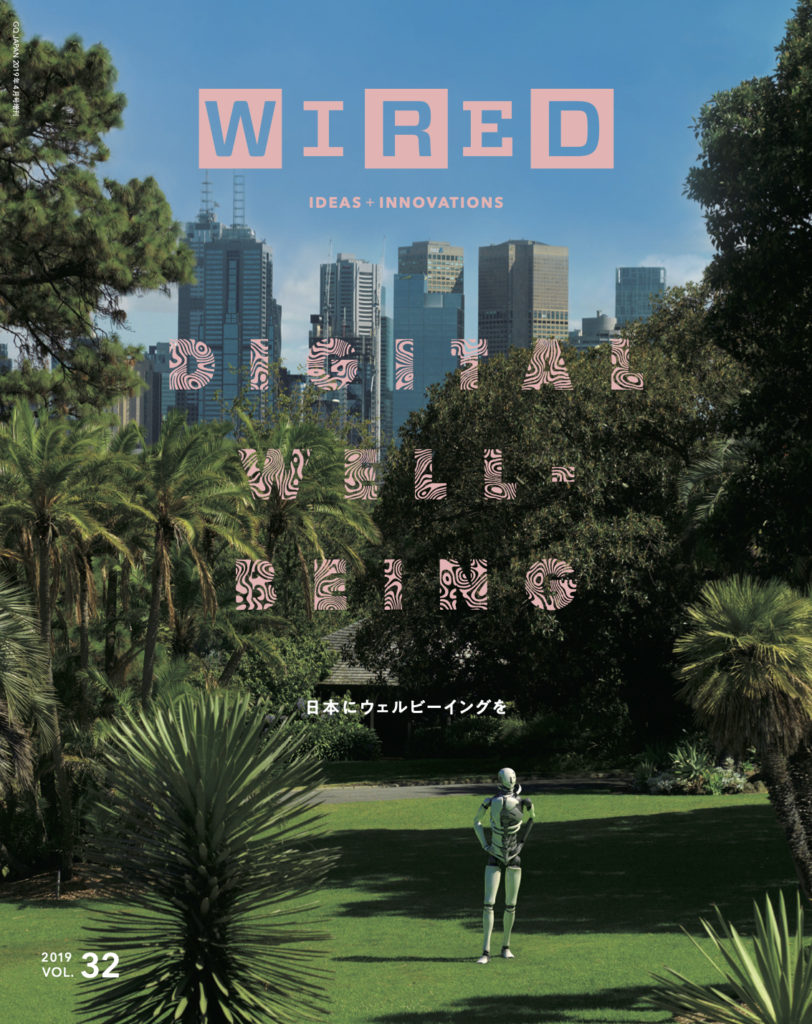
いまSNSのタイムラインを見ていると、なんでもない日常がたくさん上がっていて、僕は悪くないなと思っているんです。一昔前は何かすごいことをした人がポストして、みんなでそれを「すごい!」と褒め称えて、一方で「自分は何もできていないな」と劣等感を募らせていくのがFacebookだったと思うんだけれど、それが変化してきて、なにげない日常をシェアするようになったことはいいことなんじゃないかな。
生活自体、鶏を飼ったり裏山にちょっと行ったりすることが日常とフラットに繋がったのは、もしかしたらコロナがもたらした良い影響のひとつなのかなと思います。
最後に日常の中での「気づきのキーワード」があれば教えていただけますか。
千代田:すごく個人的なことなんだけれどいいですか? 「いま生きているな」と実感するような気持ちいい風を受けることがあるんですよ。ボブディランの歌に「風に吹かれて」ってあるじゃないですか。あの歌詞みたいに。
たとえば午前中にトレイルを走った後、シャワーを浴びて、湯上がりに昼下がりの風が吹いたりすると、素晴らしい爽快感が得られて「自分の人生って悪くないな」って思うんですね。心地よい風を感じているときってどこか俯瞰している自分がいる。ほかにも、大きな仕事を終えた時、立ち止まって風を感じて「今日は大変だったけど、自分は間違っていなかったな」と思える瞬間とか。
だから僕にとってのキーワードは「いい風感じているとき」ですかね。その風を人生で何度も感じたいって思うんですよ。気温とか湿度とか標高とか数値化できるものじゃなくて、自分の気持ちが高揚していないと感じない風。僕はその風に名前をつけたいくらいなんだけれど。
年に何回その爽快な風を感じているかが自分にとってのバロメーターになっている気がしますね。もしかしたら「決算よかったー」と思う瞬間もそうかもしれないけど(笑)。何かにチャレンジして答え合わせをして、少し時間が経ったときに「あ、これでよかったんだな」という感覚。すごく抽象的で「お前何を言ってるんだ」という話で申し訳ないんですけど(笑)。

松島:なんかそれ格好いいね(笑)。いまの話を聞いて感じたんだけれど、僕にとっては庭でのんびりできる日とか、海に夕日を見に行く日とか、そういう日ってすごくいい日だなって思うんです。
なんてことないことなんですよ、どちらも。庭なんて15歩で出られるんだけれど、日々の生活に追われているとそれができない。僕は夕暮れが好きだから、夕暮れどきの海に行って稲村ヶ崎や富士山のシルエットを見たり、庭でビールを飲んだりする時間が最高だなって思うんです。
『WIRED』の編集長に就任してからは意外にそういう何気ないことができなくなっていて、年に10回とかかな。それができるということに、ちゃんと感謝する意識を持っていたいなと思いますね。カート・ヴォネガットの本の中に「これが幸せでなきゃ、いったい何が幸せだっていうんだ」という台詞があるんだけれど、庭でビールを飲んでいるときの感覚がまさにそれで。そのときの食事は全然豪華なものじゃなくてもいいんですよ。こういう時間を持てるかどうかは精神的な意味でも自分のなかでバロメーターになっているかもしれないな。
千代田:僕も風を感じたときには心が柔らかくなって、優しい気持ちになるんですよ。なんだか似ていますね。
